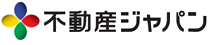トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金1.住まいを貸すときの税金
3.住まいの税金
住まいを貸すときには、不動産所得にかかわる所得税や住民税がかかります。
個人が不動産を貸して家賃を受け取る場合、その不動産の賃貸にかかわる利益は「不動産所得」となります。不動産所得は、不動産を貸して得た収入から必要経費を差し引いた額となります。
- 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
不動産所得を、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して課税総所得額を計算し、それに所得税率を乗じたものが所得税となります。
- 所得税額=(不動産所得+給与所得や事業所得などその他の所得)×所得税率
総収入金額について
総収入金額には、通常の家賃のほかに次のような収入も含まれます。
- 名義書換料、承諾料、頭金、礼金などの名目で受けとるもの
- 敷金や保証金などのうち、契約当初から返還の必要ないものや、その後に返還を要しなくなったもの
- 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費について
必要経費とは不動産収入を得るために必要な費用をいい、例えば次のようなものがあります。
- 固定資産税、不動産取得税、登録免許税
- 損害保険料
- 入居者を募集するための費用(仲介手数料、広告費等)
- 減価償却費
- 管理費、修繕費
- 不動産所得が生じる土地建物を取得するための借入金の利子(賃貸期間中)
- 家事費と業務上必要な経費にまたがる接待費・交際費・水道光熱費・電話代、地代家賃等のうち不動産貸付業務の遂行上必要で、家事費と線引きできる場合の金額
- 一の計画に基づいて同一の資産に対して行われる一の修理について次の金額のいずれかに該当する金額
- 年20万円未満の改良費
- 3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績などからみて明らかである場合の金額
- 修繕費か資本的支出かわからない金額で、一の計画に基づいて同一の資産に対して行われる一の修理について次の金額のいずれかに該当する金額
- 60万円未満である場合
- その建物等の資産の前年末の取得価額のおおむね10%未満の金額
<必要経費として認められない例>
- (1)
- 不動産所有者自身の生活費、住宅にかかる諸費用などの家事費
- (2)
- 賃貸物件の修繕費のうち、「資本的支出」に該当するもの
賃貸物件の修繕のために支出した金額のうち、それまでの物件の価値を維持するための修繕費については必要経費に算入されますが、新たに設備や機能を付け加えるといった価値を高める「資本的支出」については必要経費とはならず、物件の取得原価に算入されて、減価償却がなされます。減価償却とは、建物や設備等について、経年減価を想定して、毎年の経費として、取得価額からその額を差し引くことです。
損益通算について
損益通算とは、2種類以上の所得がある場合に、一定の順序にしたがって、その黒字や赤字の差引計算を行うというものです。
不動産所得についても、赤字となった場合には損益通算が認められていますが、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができませんので注意が必要です。
- 別荘などの生活に通常必要でない資産の貸し付けにかかわるもの
- 土地(借地権などを含みます)を取得するために負担した負債の利子の金額で一定のもの
- 一定の組合契約に基づいて営まれる不動産貸付等の事業から生じたもので、その組合の業務の執行に関与などしない特定組合員にかかわるもの
不動産所得の特例
不動産所得の赤字のうち、土地を取得するための借入金の支払利子部分は、損益通算ができません。
ただし、建物の取得にかかわる借入金利子は、損益通算ができます。
なお、土地と建物を自己資金と借入金によって取得した場合は、借入金は、まず建物の取得に充てたものと考えます。
表は横にスクロールできます。
| ケース | 損益通算可能な額 |
|---|---|
|
(不動産損失-土地借入金利子にかかわる経費)>0 不動産所得の赤字が、土地等を取得するための借入金利子よりも多い場合 |
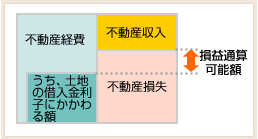 不動産所得の赤字のうち、土地の借入金利子に相当する金額は損益通算できません。 不動産所得の赤字のうち、土地の借入金利子に相当する金額は損益通算できません。土地の借入金利子以外の赤字は損益通算できます。 |
|
(不動産損失-土地借入金利子にかかわる経費)<0 不動産所得の赤字が、土地等を取得するための借入金利子よりも少ない場合 |
 不動産所得の赤字はすべて切り捨てられ、損益通算できません。 不動産所得の赤字はすべて切り捨てられ、損益通算できません。 |
青色申告の純損失の繰り越し
個人が青色申告をしている場合で、損益通算してもなお引ききれない赤字があるときは、翌年からさらに3年にわたって繰り越すことができます。
所得税の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の方法があります。
青色申告は、納税者の帳簿書類の備え付けと取引の正確な記録を促進するために、一定の帳簿書類の備え付けと相応の記帳を義務づけるとともに、各種の特典を設けている制度です。
青色申告のメリット
- 青色事業専従者給与の必要経費計上
家族従業員については、原則必要経費になりませんが、以下の場合には経費として認められます。(1) 不動産オーナーと生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上に支払った給与であること (2) その事業に専従している(年間で6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事している)こと (3) 「青色事業専従者給与に関する届出書」に支払った給与の額を記載して税務署に提出していること (4) 労務の対価として適正な金額であること なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
- 青色申告特別控除
所得金額から65万円または55万円、10万円のいずれかが控除されます。(1) 55万円の青色申告特別控除の要件
- (ア)
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業※を営んでいること
- (イ)
- これらの所得にかかわる取引を正規の簿記の原則により記帳していること
- (ウ)
- イの記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出すること
※不動産所得または事業所得を生ずべき事業:事業的規模と認められる基準は、貸家の場合、「独立家屋なら5棟以上」「アパート等なら10室以上」とされ、これらの基準以上の規模であれば、おおむね事業的規模と認められます。 (2) 65万円の青色申告特別控除の要件
55万円の要件を満たした上で、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- (ア)
- その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)に定めるところにより電磁的記録の備え付け及び保存を行っていること
- (イ)
- その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと
(3) 10万円の青色申告特別控除の要件
(1)の要件に該当しない青色申告者が対象となります。 - 家事関連費の必要経費計上
家事費は原則として必要経費とは認められませんが、青色申告者など、以下の場合には必要経費として認められます。- (1)
- 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
- (2)
- 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
- 純損失の繰越控除と繰戻還付
事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰り越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
青色申告の手続き
青色申告の適用を受けるためには、その年の3月15日までに所轄税務署に「青色申告の承認申請書」を提出し、さらに法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ一定期間(原則7年間)保存することが必要です。
青色申告承認申請のほか、不動産賃貸業の開業時には税務署に「個人事業の開廃業等届出書」その他一定の届出や申請を所轄税務署にする必要があります。
前々年の課税売上高が1,000万円超の場合には消費税の納税義務が生じます。不動産賃貸の場合には、住宅の貸し付けにかかる賃料には消費税は非課税ですが、商業ビルや駐車場の貸し付けにかかる賃料には消費税がかかります。
ただし前々年の課税売上高が1,000万円以下でも、前年の1月~6月まで期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、この課税期間から課税事業者となります。
インボイス制度について
貸店舗などの事業用不動産の賃貸借では、賃料に消費税がかかります。この場合、賃借人が納付する消費税の計算上、賃料の消費税の仕入税額控除を認めてもらうには、2023年10月1日からは、税務署に認められた所定の貸主から適格請求書をもらわないといけなくなっています。
消費税は、課税事業者において、原則として課税期間中の課税売上げにかかる消費税から、課税仕入れ等にかかる消費税を控除して、納める消費税額又は還付される消費税額を計算します。課税仕入れ等にかかった消費税額を控除することを仕入税額控除といいます。適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、消費税が複数税率になっていることに対応した消費税の仕入税額控除の方式です。具体的には、次の通りです。
| (1) | 書類の作成者の氏名又は名称、適格請求書発行事業者の登録番号 |
| (2) | 課税資産の譲渡等(取引)を行った年月日 |
| (3) | 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務(取引)の内容 |
| (4) | 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等(取引)の対価の額 |
| (5) | 適用税率及び適用税率ごとに区分して消費税額 |
| (6) | 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 |
貸店舗などの貸主が適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者であれば、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受けることが必要です。適格請求書発行事業者になると、取引先の求めに応じて適格請求書を出す義務、保存する義務を負うことになります。
●国税庁 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
貸主が消費税の免税事業者である場合には、原則として課税事業者になるため課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要があります。
借主側では、適格請求書発行事業者である貸主から適格請求書等をもらって保存することが、仕入税額控除を認めてもらうための条件です。貸主が免税事業者などの適格請求書発行事業者でない場合には、課税仕入れをしたとしても、原則として賃料にかかる消費税を仕入税額控除することは認めてもらえません。
なお時限措置(2023年10月1日から2026年9月30日まで)で、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる人については、仕入税額控除の金額を課税仕入れ等にかかる消費税額の2割とすることができる特例が用意されています。
●国税庁 「2割特例の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 住まいの税金トップ

- 1. 住まいを買うときにかかる税金
- 2. 住まいを買うときの贈与にかかる税金
- 3. 住宅ローン控除など
- 4. 住まいを保有するとかかる税金

- 1. リフォームで利用できる優遇税制
- 2. 耐震リフォームに対する減税制度
- 3. バリアフリーリフォームに対する減税制度
- 4. 省エネリフォームに対する減税制度
- 5. 同居対応リフォームに対する減税制度
- 6. 長期優良住宅化リフォームに対する減税制度
- 7. 子育て対応リフォームに対する減税制度

- 1. 譲渡所得税・住民税の計算
- 2. 譲渡して利益が出た場合の特例
- 3. 譲渡して損失が出た場合の特例
- 4. 被相続人の住まいを売る場合の特例

- 1. 住まいを貸すときの税金