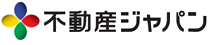空き家・所有者不明土地等対策 情報提供サイト > 国・自治体の取り組み > ⑤今後の空き家対策の方向性
1.国における取り組み
⑤今後の空き家対策の方向性
国や自治体において様々な空き家対策の取り組みが進んできましたが、今後の更なる空き家の増加や、所有者における管理や利活用が必ずしも進んでいない状況を踏まえ、国は今後の空き家対策のあり方を示しています。2023年2月に公表された「社会資本整備審議会住宅宅地分科会・空き家対策小委員会とりまとめ」によると、今後の対策として大きく4つの方針が掲げられています(図表5)。
「①発生抑制」は、住宅所有者が亡くなった後も空き家にしないよう、終活の一環として空き家対策の重要性を啓発するものです。具体的には、遺言や民事信託、生前贈与などの対処方法や、空き家化による資産価値の低減等のリスクに関する情報提供が挙げられます。そのため、啓発ツールの作成・普及や自治体・NPO等によるセミナー・相談会の開催、リバースモーゲージの活用円滑化などの取り組みが示されています。
「②活用促進」は、相続人への意識啓発や空き家の流通・活用等を促すものです。相続時の行政手続の際に、自治体・NPO等が空き家の管理負担リスクや相談先を周知させ、自らの活用や早期譲渡を促す取り組みが挙げられます。また、空き家バンクへの登録や自治会による活用の働きかけ、自治体・NPO・民間事業者が連携した協議会等による活用需要の掘り起こしやマッチングを図ることなどが示されています。
「③適切な管理・除却の促進」では、所有者の主体的な対応を後押しする取り組みとして、所有者の管理責務の意識を醸成する指針の作成や、自治体・NPO等から所有者への適切な管理の働きかけ、予算措置等による活用困難な空き家の除却への支援強化が挙げられています。また、市区町村による所有者把握の円滑化や、特定空家等の状態となるおそれのある空き家所有者に適切な管理を促す仕組み(固定資産税の住宅用地特例の解除等)も示されています。
「④NPO等の民間主体やコミュニティの活動促進」では、市区町村を補完するNPO等による空き家の活用や管理の相談対応、活用希望者とのマッチング等を促す環境整備が挙げられています。また、地域コミュニティの担い手である自治会等から所有者への働きかけを促す方針も示されています。
上記の方針を踏まえて、空き家対策特別措置法の改正案が2023年の通常国会に提出される予定です。改正案では、特定空家の予備軍となる管理不全空き家に対する税制優遇の見直しや、一定エリアにおける重点的な空き家活用策の導入、市区町村による特定空家に対する緊急時の代執行の円滑化などが見込まれており、今後の空き家対策の内容について注視する必要があります。
「社会資本整備審議会住宅宅地分科会・空き家対策小委員会とりまとめ」内容の詳細ページ
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000208.html