トップ>不動産トピックス>「フラット35(買取型)」が建設費・購入価額の10割まで借り入れ可能に
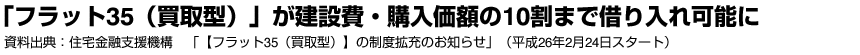
住宅金融支援機構は、平成25年度補正予算(平成26年2月6日成立)を受けて、「【フラット35(買取型)】の融資率上限の引き上げの実施」について発表した。
住宅金融支援機構によると、平成26年2月24日以降に融資資金を受け取る分から「フラット35(買取型)」の融資率上限を引き上げる。
「フラット35」は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携する長期固定金利型の住宅ローン。融資資金の受け取り時から返済完了時まで、金利が固定されるのが最大の特徴。同機構が提携金融機関の融資した住宅ローンを買い取り、証券化の手法で資金を調達する。民間金融機関が貸し出す住宅ローンについて同機構が保険などを引き受ける「フラット35(保証型)」に対して、「フラット35(買取型)」と呼ばれる。
これまでは、100万円以上8,000万円以下の範囲で、住宅の建設費または購入価額の9割までが融資率の上限だった。利用者のニーズの多様化に対応するため、頭金がなくても借り入れができるように、10割まで融資率を引き上げる。
ただし、借り換えなどで利用する場合を除き、融資率が9割以下の場合と比べると、返済の確実性などについて、より慎重に融資審査が行われるとともに、適用される金利は一定程度高く設定されることになる。なお、「フラット35」の金利は取扱金融機関によって異なる。
10割まで融資が可能になるからといって、誰もが全額借りられるわけではない。「フラット35」を利用するには、最低限の条件として、年収に占めるすべての借入金の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、一定の基準(表)を満たす必要がある。
また、「フラット35」については、同機構が定めた技術基準に適合している住宅であることや一定以上の床面積であること、住宅の建設費や購入価額が1億円以下であること、申し込み時点の年齢が70歳未満であることなどの利用条件がある。

※「フラット35」の利用条件より抜粋
→ 「フラット35」については、住宅金融支援機構の「フラット35サイト」を参照