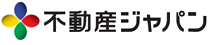トップ > 話題の不動産キーワード > VOL.81 3Dプリンター住宅
VOL.81
3Dプリンター住宅
普及へ向け、規制改革に向けた国の取り組みが本格化
執筆HFオンウェイ合同会社代表社員/「住宅新報」元編集長 福島康二
2025
10.15
3Dプリンター技術を用いてつくられる「3Dプリンター住宅」。従来の建物と比べて、自由度の高い設計やデザインが可能なほか、工期の短縮や建築コストの削減といったメリットもあり、近年、住宅市場での注目度が高まっている。国も3Dプリンター住宅の有為性に着目し、普及に向けた規制改革の取り組みを本格化している。今年(2025年)7月には、新たなコンセプトの3Dプリンター住宅も誕生するなど、事業者の動きも活発化している。
「国土交通白書」にも掲載
3Dプリンター住宅とは、デジタルデータから3次元的な物体をつくる3Dプリンターを活用して建てる住宅のこと。コンピューター上で作成した設計データに基づき、建設用の大型プリンターがノズルからモルタルなどの材料を吐出させ、自動で積み重ねて壁などをつくっていく。曲線などを用いた複雑な形状の壁でも容易につくり出せるため、独創的で個性的な住宅を建築できるメリットがある。
こうしたデザイン性の高さに加え、3Dプリンターは24時間フル稼働できることから、工期の短縮を図れるメリットがあるといわれている。さらに、建築工程の自動化による人件費の抑制など、建築コストの削減につながるメリットもある。
2024年6月に公表された「国土交通白書2024」では、セレンディクス(本社:兵庫県西宮市)が愛知県小牧市で2022年3月に竣工した、3Dプリンター住宅における省人化・省力化について触れられている。そこでは、日本初と表現している3Dプリンター住宅「serendix10」を短期間で施工した内容などに触れ、「ロボット技術が今後も進化する中で、住宅建築分野における省人化の動きが建設産業全体に浸透していき、3Dプリンターの導入による施工の効率化が主流になっていくかもしれない」とまとめられている。

イメージ画像
法規制で打ち消されるメリット
「国土交通白書」でも紹介されるなど、3Dプリンター住宅に対する注目度は高まっているものの、現在のところ日本国内での普及はそれほど進んでいない。その要因は、3Dプリンター住宅に用いられるモルタルなどの材料が、建築基準法上の構造耐力上主要な部分、すなわち構造部材として認められていないことだといわれている。現行法では、構造耐力上主要な部分などにモルタルを用いる場合、建築基準法第20条(以下、建基法20条)の規定に基づく大臣認定の取得が必要。この大臣認定を取得するには時間とコストがかかるため、工期の短縮や建築コストの削減といった、3Dプリンター住宅が持つ本来のメリットが打ち消されてしまうのだ。
大臣認定が不要になる仕様基準の創設へ
こうした状況の改善に向けて、2023年1月27日に開かれた内閣府の規制改革推進会議スタートアップ・イノベーションWGでは、「建設用3Dプリンターの活用に資する環境整備」をテーマに話し合いがもたれた。その後、2024年8月には国土交通省住宅局から、「建築物における建設用3Dプリンターの利用促進に向けた取り組み」の内容が公表された。そこでは、一例として、「モルタルで型枠を造形し、その内部に構造部材として鉄筋を配してコンクリートを充填」する場合、建基法20条による大臣認定を取得することなく、モルタルで造形した型枠も構造部材に使用できるようにする仕様規定の基準創設や、構造計算の実施に向けて当該型枠の強度指定を行う内容が記されている。実際、これらの仕様規定や強度指定にかかる基準の整備に必要な技術的知見の整理に向けた「建築基準整備促進事業(2025年度)」において、一般財団法人日本建築防災協会を事業主体に採択している。

出所:国土交通省ホームページより
「土が主原料」の3Dプリンター住宅
規制改革に向けた国の動きが本格化するなか、市場では新たなコンセプトを持つ3Dプリンター住宅が誕生し、話題を集めている。Lib
Work(本社:熊本県山鹿市)が今年(2025年)7月に完成させた「Lib Earth
House model
B」だ。同社では3Dプリンター住宅を建設する際、プリンターで外装材などとして壁をつくった後に、主要構造となる木造架構を建築する。そして一般的な内装工事を行うといった工程だが、今回の住宅では外装材となる壁に「土が主原料」の建築材料を活用した。一般的に、3Dプリンター住宅ではモルタルやコンクリートなどを建築材料に活用するケースが多いなか、同社では、土、石灰、自然繊維を配合する独自技術を開発し、必要な強度・施工性を確保したという。同社担当者は、「土、石灰、自然繊維は、いずれも地球上に豊富に存在するもの。再生可能で環境への負荷が少ない」と語る。今回の住宅は約100㎡の広さで一般販売も行う。同社では、2階建ての3Dプリンター住宅の開発も進めており、将来的にはFC展開を行い、自社開発とあわせて2040年までに累計1万棟の3Dプリンター住宅を供給したいとしている。
3Dプリンター住宅に対する市場の関心が高まっているなか、今後国内でどれだけ普及が進んでいくのか。それを左右する規制緩和がどのように進展していくのかについて、注目されるところだ。