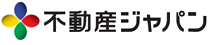トップ > 話題の不動産キーワード > VOL.61 「不動産取引の電子契約」不動産取引に必要な契約手続きがオンラインで可能に
VOL.61
不動産取引の電子契約
不動産取引に必要な契約手続きがオンラインで可能に
執筆住宅ジャーナリスト 山本久美子
2023
11.15
私たちの暮らしの中で、デジタル化が急速に進んでいる。行政のデジタル化が遅れていると指摘された政府は、デジタル庁を創設するなどでデジタル化を加速させている。対面による接客が基本である不動産業界にも、デジタル化が広がりつつある。
コロナ禍に非接触や在宅が求められると、「オンライン内見」などが普及したこともあるが、それ以前より、政府が法改正や社会実験などを重ねて、住宅の契約に関わるデジタル化を推進していることも要因だ。

出典:(公社)全国宅地建物取引業協会連合会・(公社)全国宅地建物取引業保証協会「2023年住宅居住白書」より
宅地建物取引業法の改正により電子契約が可能に
賃貸であれ売買であれ、不動産の取引には多額の費用が伴う。消費者への影響も大きいことから、宅地建物取引業法では、契約に際しては対面で行うこととされていた。具体的に言うと、契約前に知っておくべき重要な事項を宅地建物取引士が「対面」で説明すること※(これを「重要事項説明」、略して「重説」という)、さらに、「重要事項説明書」や「契約書」を書面で作成し、宅地建物取引士が記名押印したものを相手方に渡すこととされていた。 ※賃貸借契約で貸主である不動産会社が入居する借主と直接契約する場合は、重説は義務づけられていない。
対面でこうしたことを行うためには、契約者が遠方にいる場合は必ず出向かなければならない。こうした移動による負担の軽減などを求める声もあって、2015年から国土交通省はIT技術を活用した重要事項説明の社会実験を行った結果、2017年10月1日から「賃貸取引」で、2021年3月30日から「売買取引」で、IT重要事項説明が可能になった。ただし、この段階では書面への押印が必要であることに変わりはなかった。
転機となるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」だ。これを機に、2022年5月に宅地建物取引業法の改正が行われ、不動産取引の電子契約が可能になった。
●宅地建物取引業法の改正
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 押印 | 宅地建物の取引を行う際に、重要事項説明書や契約書に宅地建物取引士の記名・押印が必要 | → 押印義務の廃止 |
| 書面 | 宅地建物の取引を行う際に、重要事項説明書や契約書の書面交付が必要 | → 紙の書面に代えて電磁的方法による提供(電子書面交付)が可能 |
不動産取引の電子契約のメリットや注意点
不動産取引の電子契約とは、賃貸借契約や売買契約の際に、その契約に必要な書類を紙ではなく、電子ファイルで作成し、従来の印鑑を用いた押印の代わりに電子署名を用いることで、不動産取引に必要な契約手続きを行うことだ。
この電子契約を行うためには、当事者同士が承諾することに加えて、それを行えるIT環境が整っていることが求められる。不動産会社にとっては、紙の書類でやり取りするよりも手間や時間が軽減されるほか、契約相手が休日の日でなければ対面の調整ができないといった制約がなくなるなど、業務効率上のメリットがある。
では、契約を交わす買主や借主などの個人サイドは、どう考えているのだろう。
(公社)全国宅地建物取引業協会連合会・(公社)全国宅地建物取引業保証協会が公表した「2023年住宅居住白書」の結果を見よう。
冒頭のグラフにあるように、不動産取引の電子契約を「積極的に利用したい」(10.3%)、「どちらかと言えば利用したい」(23.8%)合わせて34.1%が利用意向を示している。なかでも、20代・30代の利用意向は半数近くにまで上がる。オンラインに慣れている若年層ほど電子契約の利用に前向きということが分かる。
次に、2022年10月に公表された(一社)不動産流通経営協会の「不動産流通業に関する消費者動向調査<第27回(2022年度)> から、電子契約に関わる設問の結果を見よう。(いずれも回答が過半数の選択肢のみ抜粋)
| ● | ITによる重要事項説明を利用したいと思う理由 |
| 「不動産会社に行く手間が省けるから」(86.1%) 「重要事項説明を実施する日程調整の幅が広がるから」(65.0%) | |
| ● | ITによる重要事項説明を利用しないと思う理由 |
| 「住宅購入に関わる大事なことなので対面での説明がよいと考えるから」(75.2%) | |
| ● | 売買契約締結時の電子署名を利用したい理由 |
| 「保管に場所を取らないから」(79.2%) 「パソコンやスマートフォンなどでいつでもどこからでも契約締結できるから」(63.0%) 「印紙税が発生せず費用負担が減るから」(62.1%) |
|
| ● | 売買契約締結時の電子署名を利用しないと思う理由 |
| 「住宅購入に関わる大事なことなので書面がよいと考えるから」(84.1%).2%) |
なお、いずれの調査結果でも利用しないと思う理由として、それらを行うための「IT環境に不安があるから」が2~3割となった。IT機器の操作や通信のトラブルなどへの不安はぬぐえないようだ。
さて、不動産取引を行う消費者にとっても、効率面でのメリットがある電子契約だが、当事者すべてでIT環境が整っていないと行えないこと、途中で通信トラブルが発生する可能性もあることなどを考慮する必要もあるだろう。電子契約を中断して環境が整ってから再開したり、最終的に書面による契約に切り替えたりといったことも選択肢に入れておいたほうがよいだろう。